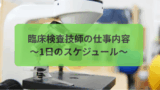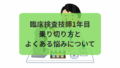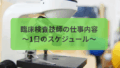医療職の中でも主に検査を担当するのが臨床検査技師です。医師や看護師ほど目立つ職種ではないため、実際どんな仕事をしているのかイメージを掴みにくいかもしれません。
そこで今回は、病院で働く臨床検査技師の仕事内容を簡単に紹介します。
僕自身も実際に病院に勤務しているので、現場の声として参考にしてみてください。
平日の日勤での業務内容
病院の検査部は部署に分かれていることが多いです。
一つの部署のみ担当する病院もあれば、複数の部署(輸血と血液掛け持ちなど)を担当するところもあります。病院によって勤務体制は少しずつ異なってきます。
ここからは各部署ごとの仕事内容を紹介していきます。
生化学・免疫検査

生化学検査という名の通り、採血検体・体液などの生化学的な検査を行います。
・検体を機械にかける
・検査結果を送信する(値がおかしければ再検査、もしくは検体の採り直しをお願いしたりする)
・機械の精度管理、メンテナンス
以上のような仕事がメインです。
現在は機械化も進み、検査自体は機械で自動で行うことが多いです。ただ、精度管理やメンテナンスなどは手動で行わなければいけません。また、検査結果のチェックも機械だけでは判別できない場合が多いので、検査技師自身が行っています。
検査結果の送信・精度管理ともに数値をチェックする仕事です。地味な仕事ではありますが、生化学検査の結果は臨床側からしても診断になくてはならないものです。縁の下の力持ち的なポジションの部署ですね。
血液・凝固検査
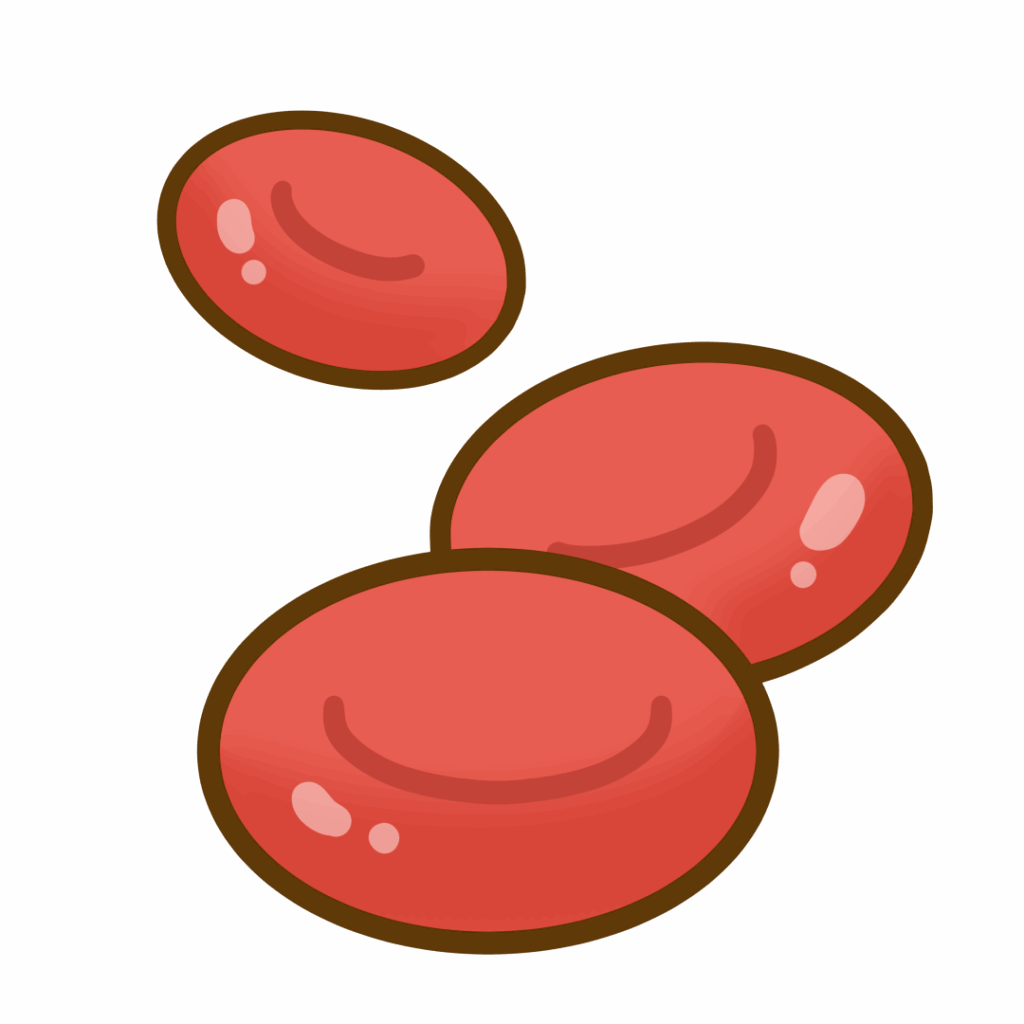
血液の分析を行います。
・血液の成分の分析(赤血球や白血球の数など)
・凝固機能の検査(血液の止まりやすさの分析など)
・骨髄検査/マルク(白血病の検査など)
血液の検査もまずは機械で行うことが多いです。機械で分析して異常な細胞などがあれば、人の目で確認します。凝固機能の検査も機械で行っているところが多いです。
また、規模の大きな病院では骨髄検査(マルク)も行っています。これは髄液を顕微鏡で鏡見し、異常な細胞がいないかチェックする検査です。主に白血病の診断に用いられます。
骨髄検査で異常な細胞を鑑別出来るようになるには経験が必要ですが、出来るようになれば一つの強みになります。
輸血検査
・血液製剤の管理(発注・入庫・払い出し)
・血液型、不規則抗体、交差適合の検査
これらの仕事を行っています。
払い出しとは、血液製剤(献血などで集まった赤血球製剤など)を手術室などに届けることです。
血液型などの検査も輸血検査の仕事です。
不規則抗体陽性の人やA型の人にB型の赤血球を輸血したりすると、患者さんにとっては生死の問題になってしまいます。患者さんの命に直結する仕事なので、責任重大な部署です。
微生物検査
2.jpg)
患者さんの検体(尿・喀痰・血液など)を専用の培地で培養して、細菌の同定や薬剤感受性を行います。
「同定」は細菌の菌種を調べること、「感受性」は抗菌薬がその菌に対して効くかを検査することです
微生物検査は時間がかかる仕事です。培養に1日〜2日、そこで生えてきた菌を検査するのに2日〜3日かかるので、長いと1週間かかることもあります。
大きな病院だと検体数も多いので、丸一日検査していることもあります。
ただ、いろいろな菌や症例を目にすることができ、奥深い分野でもあります。探究心が強い人にはぴったりな仕事です。
一般検査
主に尿検査を行います。尿に含まれる成分の検査(定性検査)と、尿中にどんな細胞がいるか(尿沈渣)を検査しています。
尿中には異型細胞(いわゆるがん細胞)も出てくるので、それらのスクリーニング検査も行っています。
また、便潜血や寄生虫の検査を行うのも一般検査の仕事です。
尿検査は機械化が進んでいますが、異型細胞の鑑別などは機械だけでは不十分です。人の手がまだ必要な分野です。
病理検査
患者さんから採取した組織などを顕微鏡で鏡見し、がん細胞がいないか検査しています。
検査技師は「細胞診」の資格をとる人が多いです。細胞診はがん細胞のスクリーニング検査のことで、患者さんの診断につながる重要な仕事です。
患者さんから採取した組織を顕微鏡で見られるようにするのも病理検査の仕事です。組織を固定する「包埋」や薄くスライスする「薄切」などがそれにあたります。
また、患者さんの死因を調べるために行う「病理解剖」も仕事の一つです。病理解剖では病理医の補助を行います。
生理機能検査

・エコー検査
・心電図検査
・呼吸機能検査
・脳波検査
以上がメインの仕事ですが、検査項目は他にもあります。患者さんに接する機会が多く、さまざまな検査を行うのが生理機能検査の特徴です。
中でもエコー検査は機械化が進んでおらず経験が必要なため、エコー検査のできる検査技師は重宝されます。エコーのスキルがあると転職でも有利なので、機会があればエコーの資格はぜひ取得しておきたいですね。
採血

採血業務も臨床検査技師の仕事の一つです。
検査技師は院内であれば採血のできる職種です。医師・看護師の負担軽減のために、検査技師が採血を行っている病院がほとんどです。
中途採用では採血経験があることを前提としている場合も多いので、検査技師になったら出来るだけ採血が出来るようになっておきたいです。
当直・日直の業務内容【夜間・休日】
病院だと夜間・休日に当直や日直を行っているところも多いです。
日当直ではいつもより検査項目を減らして対応しています。その代わり、普段は生化学などの検体検査を行っていない技師(生理機能検査の技師など)も、検体検査を担当することがあります。
・検体検査(生化学・血液・尿など)
・輸血検査
・精度管理
日当直ではこれらの業務を行う病院が多いです。
特に輸血検査は緊急で手術が入ったりすると忙しくなるので、日当直項目の中でも負担の大きい業務ですね。
仕事は忙しい?残業はどれぐらい?
病院で勤務する場合、午前中は忙しく午後は落ち着くことが多いです。
また、月初めは患者数も多いので忙しいですが、月末になるにつれて外来の数も減ってくるので仕事も落ち着いてきます。
忙しさは病院の規模によります。特に大きな病院だと、検体数も多いので毎日残業することもよくあります。
ただ、他の職業(医療職以外)と比べると残業は少ない方だと思います。他の病院の様子を聞いても、1日の残業は多くて2時間ほどです。
やりがいを感じるのはどんな時?
僕が病院で働いていてやりがいを感じたのは、採血で患者さんに感謝の言葉をもらった時です。採血をしているといろいろな患者さんに出会いますが、感謝の言葉をいただけると嬉しいですね。
また、やりがいとは少し違いますが、教科書でしか見ないような症例に出会うとやっていて良かったなと感じます。
僕は微生物検査と一般検査を担当していますが、アニサキスやカンピロバクターなど普段耳にはするけど実際に目にすることがない寄生虫・細菌に出会うことがたまにあります。初めて目にすると「もっと知識を深めたいな」と意欲が湧いてきますね。
まとめ
臨床検査技師は検査全般を担当するので、業務内容も多いです。それに加えて日当直もあります。担当する検査も患者さんの診断につながるので責任も重いです。
覚えることが多く責任感も持たなければいけないため、負担は大きい仕事です。
ただ、患者さんの診断に役立つことができ、医療現場の一員として活躍することができるため、やりがいも感じられる職業です。
医療に興味がある人には選択肢の一つとしておすすめな職業ですよ。
◆関連記事◆